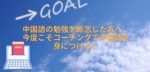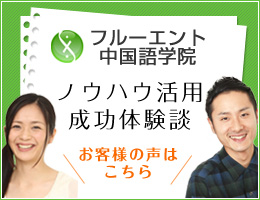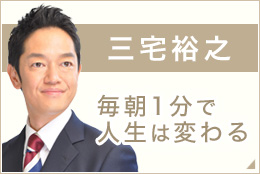このページでは、初心者から既に勉強中という方まで中国語の勉強法に役立つ情報を詳しく紹介しています。
- 初心者は何をやったらいいのか分からない
- 中国語の発音が上手くできない
- リスニングに強くなりたい
- どの参考書がいいか知りたい
- 勉強に便利なツールが知りたい
- ビジネスに必要な中国語を覚えたい
- 楽しく勉強したい
- 一番効率のいい勉強法で勉強したい……
- 勉強してもすぐ挫折してしまう
このページでは、総合的な勉強法から、発音や単語などの効率的な勉強のやり方、動画やアプリなどの学習ツール、北京語や広東語などの地域による中国語の違い、さらには留学や効率的に勉強した方々の体験談などなど…
中国語の勉強法を網羅した情報をまとめました。
どうやって勉強したらよいか悩んでいる方・自分に合った勉強法を知りたい方は必見! 必要な情報をGETしてくださいね。
目次
1.総合的な中国語の勉強法
初心者から中国語学習経験のある方へ、中国語のプロがおすすめする中国語の勉強法をまとめました。
フルーエント中国語学院学長である三宅裕之の「最強の勉強法」の要点をまとめた記事は、中国語をマスターするためには必ず読んでいただきたい内容です。必ず中国語をマスターしたい!という方は是非ご覧ください。
1-1.まずは中国語の基本を抑えよう
どうやって勉強を始めていいか分からないという方はこちらからご覧ください。
中国語の初心者・経験者も必見!
1-2.中国語の特徴を知ることが効率的な勉強の近道
漢字を知っている日本人にとって中国語の学習は有利です!
中国語の特徴をつかむことでもっと効率的な勉強が進められます。
中国語の特徴がわかると勉強は面白い
1-3.中国語ができると有利
英語が話せる方は多いけれど、中国語を話せる方はまだわずか。
そんな中国語をマスターをすることは就職・ビジネスをはじめ、日常生活においても有利なことがたくさんあります。
中国語の需要はますます増える
2.中国語の発音
中国語にはピンインというローマ字の発音記号があったり、四声という音程の上げ下げがあるのが特徴です。
日本人には発声が難しい発音もあるので、ピンインと発音の壁にぶつかる人が多いのですが、この章では、日本人が中国語の発音を無駄なくマスターできるポイントなどをまとめています。
中国語を流暢に話せるようになりたい!ネイティブに通じる発音を身につけるには、シャドーイングがおすすめ。
2-1.ピンイン
ピンインとは「中国語の発音表記法」のことで、簡単に言うと漢字の読み方をアルファベットなどで示した一種の発音記号です。
母音が36個と子音が21個あり、これらが組み合わさって、約400の音になります。
ピンインの覚え方、発音のやり方はこちらをご覧ください。
2-2.発音
中国語の学習で挫折する人が多いのは、中国語の「発音」で躓く人が圧倒的に多いのが理由です。中国ゼミの紹介するこの勉強なら苦手な発音も克服できます!
もっと簡単に発音を理解したい方必見
難しい発音のコツ
3.悩み別勉強法
単語・リスニング・リーディングの学習に役立つ情報をまとめています。 こちらを参考に苦手を克服しましょう!
3-1.単語
単語の覚え方
3-2.リスニング
3-3.リーディング
4.便利なツール・アイテム
ノートや参考書、辞書などに加え、今ではスマホの機能やアプリなど、学習や実践で役立つ便利なツールがたくさん出ています。
この章では、中国ゼミおすすめのツールや効率的な使い方についてまとめました。
4-1.辞書
語学の学習に辞書は必須ですね。今はスマホやアプリでも辞書機能を使うことができます。集中して、辞書機能のみ使いたい方には電子辞書もやっぱりおすすめ。中国ゼミのおすすめはこちらの記事をご覧ください。
4-2.本・教材
中国語の単語帳「話す・聴く・読む・書く」力を同時にアップさせるためのテキストや教材と勉強への活用方法をご紹介しています
4-3.ノート
学習ノートは作っただけで満足では肝心の中国語力は伸びません。
中国語を中国語を効率的覚える・使えるためのノートの作り方を伝授します。
4-4.アプリ・サイト
無料でも中国語が学べるサイトやアプリはたくさんあります!世界中どこにいても中国語の環境をいつでも作ることは可能。
中国ゼミがおすすめする中国語の勉強アプリをご紹介しています。
4-5.PC・スマホ入力
今や、オンラインでのコミュニケーションは必須。中国語を入力できるようになるためのお持ちのPCやスマホの環境設定やピンインの入力方法をお教えします!
5.動画・講座
コロナウイルスの影響でのステイホーム期間に、ぐっと身近になったオンライン講座や動画。
たくさんある中でも人気のものや、中国ゼミスタッフが実際に見ている・使っているものをまとめました。
6.文字・方言
中国語には地方によって違いがあり、文字から異なります。方言と呼んだり、全く別の言語として扱われていたりと、日本人にはちょっと理解できないこともあるかもしれません。
香港や台湾、シンガポールでも中国語が公用語としてしようされています。
それぞれの特徴も記事で分かりやすくまとめました。
7.留学・体験談
中国ゼミスタッフが実際に中国留学をしてみて分かった、中国の大学の雰囲気や留学中の過ごし方をご紹介します。
また、フルーエント中国語学院で中国語をマスターした方のリアルな声もお届けします。