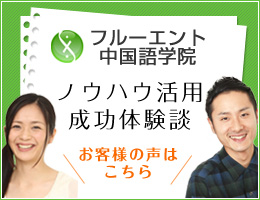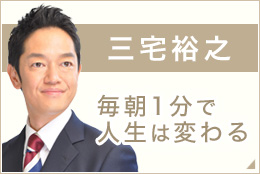中国語の声調の中でも、第3声を苦手とする日本人が多くいます。なぜなら、第3声は後ろに来る言葉によって声調を変化させる必要があったり、第2声との区別が難しかったりと、悩むところが他の声調よりも多くあるからです。
この記事では、「第3声の発音が上手く発音できない」悩みを抱えるあなたのために、第3声のポイントや練習法を分かりやすく解説していきます!
その答えを、90分の無料セミナーで
解説します。
「中国語が伸びない…」
それ、努力不足ではありません。
勉強法を変えるだけで、
効率は4倍まで上げられます。
目次
1.中国語の第3声とは
中国語には、声調と呼ばれる中国語の発音における音程の上げ下げがあり、パターンが4種類あるので、「四声」と呼ばれています。
中国語はこの四声を正しく発音できないと相手に意味が伝わらないため、正しく発音する必要があります。中でも、第3声は日本人には苦手な発音なのでしっかりマスターしましょう。
第3声の発音は、低い音から始まって低いところで終わるのが特徴です。
声調記号を見ると下がってからまた上がるように記載されています。しかし、最後は上げるというよりも、声を低く抑えて最後に力を抜くとき少し上がるように聞こえると思ってください。
日本語で言うとがっかりしたときの「あ~あ」のイメージが近いです。
| 馬 mǎ 马 マー |
以前、私(中国在住、中国ゼミライターS.I.)は好物のスモモを買おうと思い、果物店で店員さんに「李子有吗?(スモモはありますか?)」と聞いたところ、最初に出てきた果物は梨でした。もう一度聞いてみたところ、次に出てきた果物は栗。。
私が声調を上手く発音出来なかったため、スモモの「李子(lǐzi リーズー):第3声」と、梨の「梨子(lízi リーズー):第2声」、栗の「栗子(lìzi リーズー:第4声)」を聞き間違えられてしまったのです。その後、店員さんにジェスチャー付きで声調をしっかり直していただきました。
皆さんも違いを確認してみてください。
| スモモ(第3声) lǐzi 李子 リーズー |
| 梨(第2声) lízi 梨子 リーズー |
| 栗(第4声) lìzi 栗子 リーズー |
私のように声調を間違えると全く違う意味として伝わり、欲しいものが買えない…なんて事態になるかも。そのくらい、中国語の発音で「正しい声調」は大切です!
四声を動画で説明しているこちらもチェックしてみてください。
発音を参考にしながら練習できるこちらもおすすめ!
効率4倍アップの勉強法セミナーに
参加していただけませんか?
今の勉強法を続ける前に、
一度だけ「正解」を確認しませんか?
✔ 話す・聞く・読む・書くが同時に伸びる
✔ 効率4倍アップの学習設計
✔ 90分・無料
2.第3声の組み合わせ
第3声のややこしいところのひとつは、組み合わせによって声調が変化する場合があるということです。
第3声と第1声〜第4声それぞれの組み合わせにおける単語の例と、第3声が複数続くときの声調の変化の仕方について見てみましょう。
2-1.第3声と第1声の組み合わせ
第1声との組み合わせでは、第3声は変調しません。
2-1-1.<第1声の後に第3声が来る場合>
| 冷たい水 bīng shuǐ 冰水 ビン シュイ |
| 空港 jī chǎng 机场 ジー チャン |
2-1-2.<第3声の後に第1声が来る場合>
| 携帯電話 shŏu jī 手机 ショウ ジー |
| コップ shuǐ bēi 水杯 シュイ ベイ |
2-2.第3声と第2声の組み合わせ
2-2-1.<第2声の後に第3声が来る場合>
| りんご píng guŏ 苹果 ピン グゥォ |
| 情景 qíng jǐng 情景 チン ジン |
2-2-2.<第3声の後に第2声が来る場合>
| いちご cǎo méi 草莓 ツァォ メイ |
| アメリカ Mĕi guó 美国 メイ グゥォ |
2-3.第3声+第3声の組み合わせ
2-3-1.<第3声が2つ続く場合>
| こんにちは nǐ hǎo 你好 ニー ハオ |
| 水餃子 shuǐ jiǎo 水饺 シュイ ジァォ |
| 雨傘 yŭ sǎn 雨伞 ユー サン |
2-3-2. <第3声が3つ以上続く場合>
| 小さい港 xiǎo gǎng kŏu 小港口 シァォ ガン コウ |
| 「港口」で港という1つの名詞です。意味的に、小+港口になるため「港」の部分が2声に変調します。声調は3声・2声・3声の順です。 |
| 演技者 biǎo yǎn zhĕ 表演者 ビィャォ イェン ヂェァ |
| 「表現(表演)」する「者」という意味で、表演+者になるため、まずは「表」が第2声に。そして「演」も、後ろに来る「者」を受けて第2声に。結果、全体の声調は2声・2声・3声の順になります。 |
3声が3連続までの場合は、複雑に考えずに最後の3声以外は2声に変わると考え、2声・2声・3声とスムーズに発音してみましょう。
| 私は果物が買いたい Wŏ xiǎng mǎi shuǐ guŏ 我想买水果。 ウォ シィァン マイ シュイ グゥォ |
| きちんと意味上のつながりで変調箇所を選ぶとすれば「我想买(私は買いたいと思う)+水果(りんごを)」となりますので、2声・2声・3声・2声・3声の順です。 |
このように、あまりにたくさん第3声が続くと、どれを変調させればよいか分からなくなってしまいます。厳密には、音節の意味上のつながりごとに変えた方が良いのですが、迷ってしまったときは、最後以外すべて第2声に変えてしまいましょう。もし、慣れてきたら意味のつながりを意識してみてください。
2-4.第3声+第4声の組み合わせ
2-4-1.<第3声の後に第4声が来る場合>
| メガネ yǎn jìng 眼镜 イェン ジン |
| スプライト xuĕ bì 雪碧 シュェ ビー |
2-4-2.<第4声の後に第3声が来る場合>
| 日本 Rì bĕn 日本 リー ベン |
| 分かち合う gòng xiǎng 共享 ゴン シァン |
2-5.第3声+軽声の組み合わせ
| 椅子 yǐ zi 椅子 イーズー |
| 姉 jiĕ jie 姐姐 ジェ ジェ |
3.第3声の発音を練習するコツ
第3声をどう発音するかの理論が分かったら、後は練習と実践あるのみです。第3声の発音を練習するコツについて見てみましょう。
3-1.第3声を単独で発音練習する
第3声を発音するポイントは、一番低い音程まで声を下げてから軽く上げることです。最後を軽く上げるといっても、発音記号のようにV字型に下がって上がる必要はありません。
喉に力を入れて低く下げ切り、最後にふっと力を抜いた時に自然に上がる程度だと思ってください。
3-2.第3声の連続による変調の発音練習
<第3声の後ろに第3声以外の声調が来る場合>
| 第3声を「半3声」にします。つまり、低い音程で第3声を発音したら、最後に軽く上げる段階に至らずに、そのまま次の声調に移行しましょう |
<第3声が続く場合>
| 前の第3声を第2声に変調して発音します。第3声が2つの場合は前のものを第2声に、3つ以上続く場合には音節の意味のつながりによって、どこを変調させるのがよいか判断しましょう。(詳しくは「2-3.第3声+第3声の組み合わせ」を参考) |
頭で理解するのも大切ですが、教材の録音を繰り返し聞いて自分でも繰り返し発音してみたり、中国語でたくさん交流して実践することが最重要です。
たとえば「我想买~(Wǒ xiǎng mǎi ウォ シィァン マイ)」「请给我〜(Qǐng gěi wǒ チン ゲイ ウォ)」などのフレーズは自然に変調させて話すことができるようになってきます。
3-3.発音を練習するおすすめの方法
第3声の練習ができたら、第3声を含む全体の練習を行いましょう。日本人が中国語の発音を練習する際におすすめの方法を紹介します。
3-3-1.声を大きくはっきりと
日本人が中国語を話そうとすると、声が小さく抑揚が少ない、はっきりしない感じになりがちです。練習の時はとくに、大げさかなと思えるくらい声を大きく、口の開け閉めや声調も必要以上にはっきりと行いましょう。
3-3-2.自分の苦手を知る
教材の録音と自分の発音を聞き比べるなどして、自分が苦手な音や声調を知りましょう。自分のレベルに合った中国語の文章を用意し、自分の苦手な発音・声調の部分に印をつけたうえで、何度も朗読します。聞いてくれるネイティブの友達がいればベストですが、自分の声を録音して自分で聞いてみるのもよいでしょう。
中国ゼミでは、シャドーイングをおすすめしています。シャドーイングとは、耳で聞いて聞こえた音を影のように真似して発話する方法です。シャドーイングをすることで、中国語のフレーズと意味を丸ごと覚えられ、聞く・話す・読むの力を同時に鍛えることができます。聞いた時に日本語に変換して理解するのではなく、中国語のまま理解できるようになるので、中国語への反応も早くなります。
それではシャドーイングの手順をご説明していきます。
| ステップ1 |
| 音だけ聞いてリスニングする この時点では音を聞くだけで大丈夫です。自分がどのくらい聞き取れるか確認しましょう。 |
| ステップ2 |
| 内容・意味を理解する 本文を読み内容を理解します。分からないところは教材に意味や発音、記号を書き込み、自分専用の「楽譜」のようにしていきます。 |
| ステップ3 |
| ピンインを見ながらシャドーイングする 教材のピンインを見ながらシャドーイングしていきます。この作業を10回ほど繰り返して行います。 |
| ステップ4 |
| 漢字を見ながらシャドーイングする 今度はピンインを見ずに、漢字だけを見てシャドーイングします。聞こえた通りにシャドーイングするのがポイントです。 |
| ステップ5 |
| 何も見ずにシャドーイングする 最後に何も見ずに聞こえた通りにシャドーイングします。慣れてきたら感情を込めて抑揚をつけながら発声します。感情が伴うと忘れにくくなるのでおすすめです。 |
こちらのページでは、シャドーイングについて更に詳しく説明しています。
効率4倍アップの勉強法セミナーに
参加していただけませんか?
今の勉強法を続ける前に、
一度だけ「正解」を確認しませんか?
✔ 話す・聞く・読む・書くが同時に伸びる
✔ 効率4倍アップの学習設計
✔ 90分・無料
3-3-3.ネイティブの発音を聞く
教材の録音を聞いたり、中国語の連続ドラマなどを視聴したりして、ネイティブの発音に触れる機会を増やしましょう。
また、ネイティブの友達ができたら、WeChatなどの文字メッセージのやり取りだけでなく、実際に会ってたくさん話をしてください。語学は実践あるのみです。
効率4倍アップの勉強法セミナーに
参加していただけませんか?
今の勉強法を続ける前に、
一度だけ「正解」を確認しませんか?
✔ 話す・聞く・読む・書くが同時に伸びる
✔ 効率4倍アップの学習設計
✔ 90分・無料
第3声の発音は発音しやすい様に変調される
中国語の学習者を戸惑わせることの多い第3声ですが、発音の特徴や組み合わせによる変化を押さえれば、それほどややこしいことはありません。問題の「変調」も、もともとは第3声の連続は発音しにくいことから、発音しやすいようにするために自然と生まれたものです。そのように考えれば、身につけやすいのではないでしょうか。
効率的に身に付けるなら、間違いを恐れず実際の会話でたくさん発音をしてみることです。積極的に会話をして、中国語でのコミュニケーションをぜひ楽しんでくださいね。
記事をお読みいただきありがとうございました。
今年こそ
「勉強しているのに話せない」を終わらせませんか?
中国語学習が伸び悩む最大の理由は、
「知識」を増やしても
音と口がつながっていないことです。
三宅式シャドーイングは、
✔ 聞く
✔ 話す
✔ 語順・表現
を同時に鍛える、最も効率の良い練習法。
本セミナーでは、
2,500人以上の指導実績をもとに、
・シャドーイングをやるべきタイミング
・効果が出る人/出ない人の決定的な違い
・HSK・検定対策とどう組み合わせるか
を具体的に解説します。
独学で限界を感じている方、
今年こそ「話せる中国語」を本気で身につけたい方は
ぜひ一度ご参加ください。
・中国語ゼミでは日本人が効率よく中国語をマスターするためのノウハウをすべてご紹介しています。ぜひ実践してください。
・また「中国語」にまつわる疑問を中国ゼミが徹底解説しています。
効率4倍アップの勉強法セミナーに
参加していただけませんか?
今の勉強法を続ける前に、
一度だけ「正解」を確認しませんか?
✔ 話す・聞く・読む・書くが同時に伸びる
✔ 効率4倍アップの学習設計
✔ 90分・無料