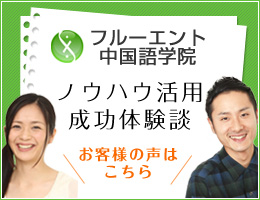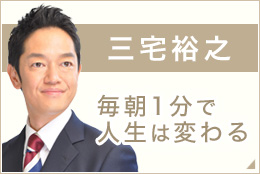「スクールに通う時間もお金もない。けれど、中国語を話せるようになりたい!」
そんなあなたに向けて、本記事では“独学で中国語を学ぶ方法”を紹介します。アプリや無料教材をどう使うか、どんな順番で進めればよいか、そしてどうすれば挫折せず続けられるか。独学成功者の実例も交えてお届けします。
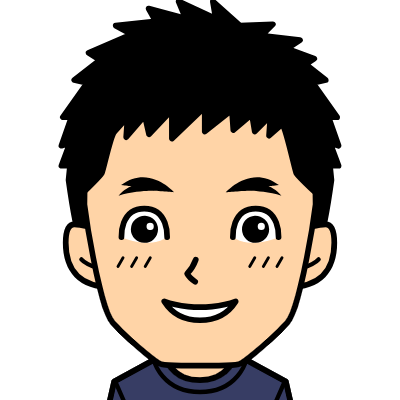
その答えを、90分の無料セミナーで
解説します。
「中国語が伸びない…」
それ、努力不足ではありません。
勉強法を変えるだけで、
効率は4倍まで上げられます。
目次
中国語を独学で学ぶときの心構え
独学で中国語を学ぼうと決めたものの、「このやり方で合っているのか?」「続けられるかな…」と不安になる方も多いはず。
まずは、独学のメリット・デメリットを知り、自分に合った学習スタイルを見つけることが成功の第一歩です。
独学のメリット・デメリット
中国語を独学で学ぶことには、自由さや低コストなどの魅力がありますが、反面、正しい方向に進められるかどうか不安を抱えながらの学習になる場合もあります。
ここでは、独学の特徴をメリット・デメリットの両面から整理してみましょう。
| 独学のメリット | 独学のデメリット |
| 自分のペースで進められる | 発音の習得が難しい |
| コストが低い | 練習バランスが取りづらい |
| 興味のある教材を選べる | モチベーション維持が困難 |
【メリット】
● 自分のペースで進められる
時間や場所に縛られず、仕事や家事の合間など自分の都合に合わせて学べるのが独学の強みです。自分なりの学習スタイルを確立しやすいのも魅力です。
● コストが低い
書籍やアプリ、無料の動画などを使えば、費用を抑えて学習できます。語学教室やオンラインレッスンと比べて経済的なのも、独学の大きな利点です。
● 興味のある教材を選べる
ドラマやアニメのセリフ、ビジネス表現など、自分が「学びたい」と思う分野に特化した教材を自由に選べます。興味がある内容だからこそ、モチベーションも維持しやすくなります。
【デメリット】
● 発音の習得が難しい(デメリット)
独学では発音のフィードバックが得づらく、間違った発音をそのまま覚えてしまうリスクがあります。発音はリスニング力にも直結するため、対策が必要です。
● 練習バランスが取りづらい(デメリット)
知識のインプットに偏りがちで、会話練習や発音練習など「使う」ためのトレーニングが不足しやすい点に注意が必要です。
● モチベーション維持が困難(デメリット)
一人で学ぶ場合、進捗が見えにくく不安になったり、挫折しやすくなることも。学習記録アプリやSNSでの発信など、継続しやすい工夫が求められます。
目標設定とモチベーション維持の10の秘訣
| 中国語学習を続ける10の工夫 |
|
✅ 1. なりたい姿を描く ✅ 2. 避けたい姿を描く ✅ 3. 強制力を味方につける ✅ 4. 悔しさをモチベーションに変える ✅ 5. 中国語試験を活用する ✅ 6. 自己理解を深める ✅ 7. スケジューリングで習慣化 ✅ 8. スキマ時間を賢く活用 ✅ 9. 学習内容(ToDo)のルーティング化 ✅ 10. 何かを手放す |
✅1.なりたい姿を描く
まずは「中国語を学んでどうなりたいか」を明確に描きましょう。
転職や昇給、現地就職、国際恋愛の成功など、目標が具体的であればあるほど、行動に移しやすくなります。
私自身、中国語ゼロからのスタートだったので、中国で就ける仕事が限られていました。ですので、「中国で職の可能性を広げたい」”手に職を”という意味でも「もしものときのために教えられるスキルも身につけたい」といった目標を定めて取り組みました。
目標は一度決めたら終わりではありません。定期的にアップデートして、進化する自分に合わせて調整していきましょう。
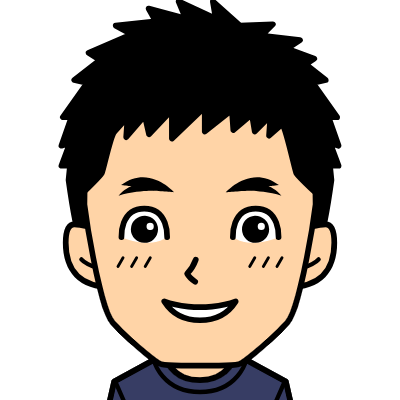
✅2.避けたい姿を描く
「なりたい自分」と同じくらい、「なりたくない自分」も学習の原動力になります。目標が曖昧な方は、「こうはなりたくない!」という姿から逆算してもOKです。
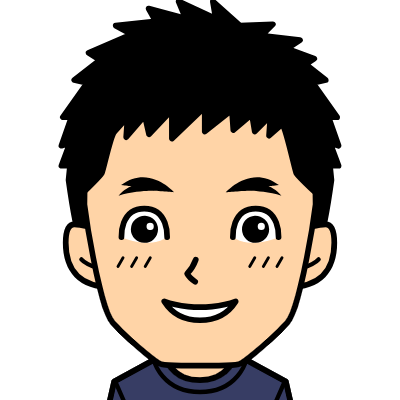
✅3. 強制力を味方につける
「やらざるを得ない環境」に自分を追い込むのも有効です。以下のようなルールを自分に課してみましょう。
「SNSで学習宣言をする」という方法は、宣言“だけ”だと満足して終わる危険性があるため、成果報告とセットにするのがベストです。
✅4. 悔しさをモチベーションに変える
言いたいことが伝えられなかったり、大事な内容を聞き取れなかったり… そんな「悔しい経験」こそ、強力なエネルギーになります。
特に勉強を始めたばかりの時期や、伸び悩みのタイミングでは、「悔しさをバネに」で行動を再起動させましょう。
✅5. 中国語試験を活用する
やる気が落ちてきたときこそ、思い切って試験に申し込んでしまいましょう!HSKや中国語検定など、「日付が決まっている目標」は集中力を生みやすいです。
すでに合格済の方は、TECCやBCTなど他の検定に挑戦してみると、よい刺激になります。
✅6. 自己理解を深める
自分がどんなときに集中しやすく、どんなときにサボりがちか、知っておくことも大切です。
「朝型が合うのか?夜型なのか?」
「スケジュールはガチガチがいい?柔軟なほうが続く?」
いろんな方法を試しながら、最適な自分スタイルを見つけましょう。
✅7. スケジューリングで習慣化
「時間ができたらやろう」ではなく、時間割のように「やる時間を先に決めておく」ことが大事です。
私は毎朝5時半に起き、出勤までの1時間半を学習時間にしていました。このように、「毎日やっている事の直後にやる」など、毎日の生活の一部に組み込むことで、「勉強しなきゃ…」というストレスも減り、自然に継続できます。
決まった時間が難しければ、「朝20分・昼20分・夜20分」など、スキマ時間を活用するのもおすすめです。
✅8. スキマ時間を賢く活用
机に向かわないとできない学習もあれば、移動中や待ち時間にできるものもあります。以下は私の例です。
|
【机でやるべきこと】 ・文章の理解(単語・文法・語順など) ・発音練習 ・声に出しての音読/リピーティング/シャドーイング ・ディクテーション 【スキマ時間で出来ること】 |
自分のスタイルに合わせて、時間の使い分けを工夫してみてください。
✅9.学習内容(ToDo)のルーティング化
勉強をする時間を固定化することに加えて、その毎日どの時間帯にどんなことをこなしていくかまでを固定できると、やはり習慣化に成功しやすくなります。
|
退勤後:机に向かっての学習の時間(教材テキストの単語・読み方・文法・語順などの理解) 翌朝:音読・シャドーイングなどの練習時間 お昼休み:音読・シャドーイングなどの練習時間 移動時間:単文暗記とエアー・クイックレスポンス 運動時間:小声でシャドーイング |
このような形で、どんなときには何をするかを完全に決めていたので、いずれも容易に習慣化させることができました。
✅10. 何かを手放す
時間は有限。新しく学習時間を確保するには、何かをやめる覚悟も必要です。
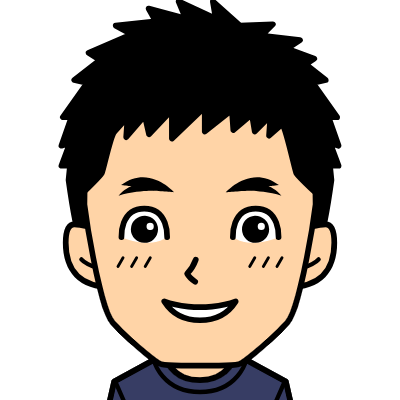
独学でやるべきこと5ステップ
~会話力を身につけるためのプロセス~
効果的に中国語を身につけるには、まず学習の全体像を理解することが大切です。特に独学では、順序を誤ると非効率になってしまいます。
多くの日本人学習者は、いきなりネイティブとの会話練習を始めてしまいがちですが、それは学習プロセスの“3番目のステップ”です。本来の流れは次の通りです
特に②の「練習」を飛ばすと、会話練習の効果が半減してしまいます。以下では、練習と実践を含めた5つのステップをご紹介します。
ステップ1 リスニング力の鍛え方
中国語の音が聞き取れない/初心者・初級者全般
会話力を高めるうえで、まず土台になるのがリスニング力です。聞き取れなければ、相手の言っていることがわからず、会話が成立しません。
独学でリスニングを鍛えるなら、次の2つの練習がおすすめです。
🟩 シャドーイング(聞いてすぐマネする練習)
もっとも効率よくリスニングを鍛える方法がシャドーイングです。教材の音声を聴き、0.5秒ほど遅れて真似しながら発音するトレーニングで、聞く力と話す力を同時に伸ばすことが出来ます。
リスニング力を伸ばすには、発音・語順・意味などを総合的に理解する必要があります。シャドーイングを繰り返すことで、これらの要素を自然に体に染み込ませていくことができます。
さらに、同じ文章を何度も発音することで口が中国語に慣れ、表現がスムーズに口をついて出るようになります。まさに、リスニングとスピーキングを一度に鍛えられる“一石二鳥”のトレーニングです。
🟩 ディクテーション(書き取りで細かく聞く練習)
ある程度、音が聴き取れるようになったら、次に試したいのが「ディクテーション」です。
音声を聴いて、そのまま一語一句を書き取る練習で、集中力と根気が必要ですが、効果は抜群です。何度も聴くことで“聴く耳”が養われ、曖昧だった音がクリアに聞き分けられるようになります。
- あまり速すぎない音声教材(スクリプト付き)
- ノート(曖昧な漢字を認識するため手書きがおすすめ)
※自分のレベルに合った教材を選びましょう。
- まずは音声を2〜3回聞いて全体をつかむ
- 一文ずつ止めながら、中国語で書き取る
- 不明な単語は音だけを頼りに調べる
- 書けなかった簡体字は復習する
- 意味が通じるか確認する
- 聴き取れなかった部分はピンインと声調で記録
- スクリプトで答え合わせ
- 最後に音読して復習
もし「全体は分かるけど細部まで聞き取れない…」と感じる方は、短い音声から始めるのがおすすめです。時間がかかる分、集中力と語彙の定着率がぐんと上がります。また、単語教材をディクテーションに回すなど、無理のない形で取り入れてみましょう。
ステップ2 スピーキング力の鍛え方
単語は覚えたけど口から出てこない人/中級を目指す人
リスニングと並んで、会話力を伸ばすうえで欠かせないのがスピーキング力です。独学でも、工夫次第で十分に鍛えることができます。
まず意識したいのは、インプットをしっかり増やすこと。そのうえで、「クイックレスポンス」と呼ばれる練習法を取り入れてみましょう。覚えた単文やフレーズを、反射的に口から出せるようにするトレーニングです。
- 単文教材や総合教材を使い、基本構文を丸ごと覚える
- 覚えた構文の一部(動詞・目的語・時間詞など)を入れ替えて応用練習する
この練習はひとりでもできますし、スキマ時間に取り組めるのも大きなメリットです。移動中に脳内で反復するだけでも、効果があります。
私も初級の頃、現地に住んでいたにもかかわらず会話がほとんど成立せず、練習相手もいなかったため、苦肉の策として始めたのが「ひとりQ&A」でした。独り言や自問自答を中国語で繰り返すことで、徐々に言葉が自然と出てくるようになり、ネイティブとの会話も怖くなくなったのです。
「話そうと思っても言葉が浮かばない」と悩む方は多いですが、それは脳内で使いたい表現が準備できていないから。この「ひとりQ&A」は、まさにその準備にぴったりな練習法です。
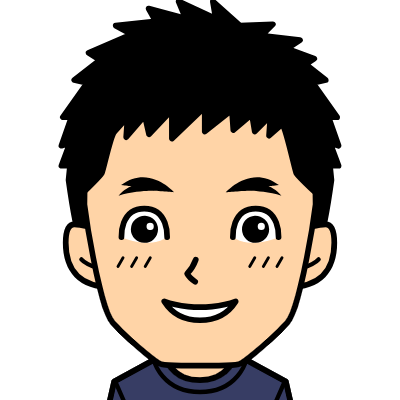
ステップ3 日記やSNSで作文練習(5行日記)
言いたいことを文章で伝える練習がしたい人/SNSを活用したい人
スピーキング力を高めるには、自分の言いたいことを表現する練習が効果的。その中でもおすすめなのが、中国語での日記やSNS投稿です。
リスニングは幅広い語彙が必要ですが、スピーキングは自分に関係のある内容だけでも十分。だからこそ、日常に沿った作文練習が役立ちます。自由な書き方だと会話に活かしにくいこともあるので、以下の「3行~5行日記」の形式がおすすめです。
5行日記テンプレート
| ① 出来事(事実) | 例:私は〜〜しました。 |
| ② 感想(気持ち) | 例:〜〜して、〇〇でした。 |
| ③ 感想2(具体例) | 例:〜〜だったので、△△と思いました。 |
| ④ 質問(問いかけ) | 例:あなたは□□ですか? |
| ⑤ 回答(仮定・実体験) | 例:私は△△で、〇〇と思います。 |
例文で見る5行日記
| ① 出来事(事実) |
私は先週北京に出張にいきました。一年ぶりです。 → 我上周去北京出差,是时隔了一年的出差。 |
| ② 感想(気持ち) |
なにも変化は感じられませんでした。 → 我感受不到什么变化。 |
| ③ 感想2(具体例) |
仲の良い友人ともたくさん会えて楽しかったです。 → 和亲密的朋友们见面并度过了愉快的时光,非常开心。 |
| ④ 質問(問いかけ) |
あなたは北京に行ったことがありますか? → 你去过北京吗? |
| ⑤ 回答(仮定・実体験) |
一年に1回は北京に行く機会があります。来月また行く予定です。 → 我一年里有一次去北京的机会。下个月也要去。 |
このように形式を決めることで、書くのがラクになり、習慣化しやすくなります。そして、そのまま会話にも応用できるのが大きなメリットです。
自分だけの日記もいいですし、公開するSNSもいいでしょう。InstagramやXだけでなく、中国のRED(小红书)やWeiboなどのSNSにトライすると作文力が爆伸びするかもしれません!
ステップ4 中国語テストで力試し
客観的にレベルを確認したい人/目標が欲しい人
語学学習を継続するには、「できるようになった」と感じられる機会が大切です。そのためにも、中国語のテストをステップアップの目安として活用してみましょう。
代表的な試験は「HSK(漢語水平考試)」です。1級から6級まであり、毎月のように試験が開催されています。各級で必要な単語数や文法力、運用力が明確に設定されているので、自分のレベルを客観的に確認できます。
日本では4級以上、中国では5級以上が履歴書などで評価対象となることもあります。
HSK以外にも、日本国内では「中国語検定」や「TECC」など、さまざまな中国語試験が実施されています。自分の目的や学習段階に合った試験を選ぶとよいでしょう。
試験を受けると決めたら、1〜2ヶ月前から過去問に取り組み、時間配分や出題傾向に慣れておくのがポイントです。
ステップ5 会話の実践相手を見つける方法
会話経験を積みたい人/アウトプットの場がない人
勉強した中国語を「実際に使う」ことは、上達に欠かせません。 ここでは、目的やレベルに応じた実践の場や会話相手の探し方をご紹介します。
✅ 店員さんと会話してみる
中華料理店や居酒屋では、中国人の店員さんと出会う機会も多いもの。勇気を出して「こんにちは」「これをください」など簡単なフレーズで話しかけてみましょう。
日常のちょっとしたやりとりも、立派な実践の場になります。
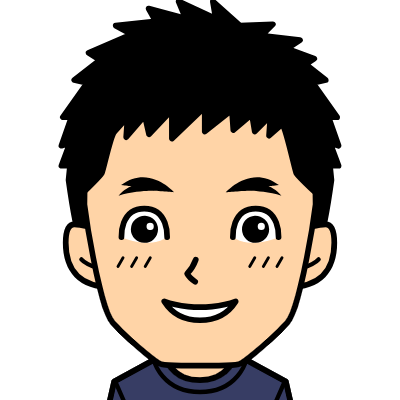
✅ 言語交換で「お互いに学ぶ」
日本語を学習している中国人と、お互いの言語を教え合う「言語交換」もおすすめです。
お金をかけずに会話の練習ができますが、以下の点には注意しましょう。
・あまりお金を掛けずに出来る
・同じ語学学習者同士なので気軽
デメリット
・相手の練習にも時間を使う必要がある
・レベル差があると会話が偏りがち
・初級者同士ではスムーズに進まないことも
アプリでは「HelloTalk」や「Tandem」が有名ですが、詐欺や不適切な目的の利用者がいる可能性もあるので、十分注意を。
✅ ネイティブ講師とのオンラインレッスン
最近は、オンラインでリーズナブルにネイティブとの会話レッスンを受けることが可能になっています。ただし、日本語が話せる講師や、こちらに配慮してくれる優しい先生だと、“会話したつもり”になりやすいかも…。
本気で話す力を伸ばしたいなら、「厳しめに訂正してください」とリクエストしてみましょう。
✅ 日中コミュニティに参加する
外国人向けのコミュニティアプリやグループで、中国人・台湾人が多く集まる場所を探すのも効果的です。ただし、「中国語の練習相手が欲しい」と最初からアピールするのはNG。
「誰でもいいから練習したい」という姿勢は、相手に不快感を与える可能性もあるので気をつけましょう。
まずは友達づくりから。会話練習はその延長として、自然にできるのが理想です。
よくある不安とその対策
発音が正しいか分からない
対策 : 発音チェック付きアプリやAIの活用
HelloChinese/SuperChineseなどのアプリは発音を自動判定機能があるのでおすすめ。
また、スマホの音声入力やChatGPTの発音フィードバック機能も活用可能です。
三日坊主になりそう
対策 : 学習記録アプリやSNSで可視化&共有
StudyPlus/Notionなどのアプリで記録・振り返りを習慣に
SNS投稿(X, Instagram)でハッシュタグ「#中国語勉強」をつけて仲間と交流するなど工夫をしてみてください。
続けるコツは 「目標設定とモチベーション維持の10の秘訣」 で詳しく紹介しています。
続ける自信がない
対策 : 習慣トリガー+”三日坊主OK”思考
「歯磨き後に5分だけ中国語」など日常行動とセットにすると続けやすくなります。
三日坊主でも、繰り返せば習慣になる
習慣化のコツは「目標設定とモチベーション維持の10の秘訣」で詳しく解説しています。
まとめ
中国語の独学は、自由度が高くコストも抑えられる反面、学習の流れを見失ったり、方法を間違えたり、モチベーションを維持しづらいという課題があります。
だからこそ、学習の全体像を把握し、レベルや目的に応じて学習方法や進め方を”戦略的にデザインする”ことが何より重要です。
独学は「自己管理」と「習慣化」がすべてと言っても過言ではありません。学習方法に迷ったときは、本記事を何度も見返して、自分の現在地を確認しながら進めていきましょう。
記事をお読みいただきありがとうございました。
今年こそ
「勉強しているのに話せない」を終わらせませんか?
中国語学習が伸び悩む最大の理由は、
「知識」を増やしても
音と口がつながっていないことです。
三宅式シャドーイングは、
✔ 聞く
✔ 話す
✔ 語順・表現
を同時に鍛える、最も効率の良い練習法。
本セミナーでは、
2,500人以上の指導実績をもとに、
・シャドーイングをやるべきタイミング
・効果が出る人/出ない人の決定的な違い
・HSK・検定対策とどう組み合わせるか
を具体的に解説します。
独学で限界を感じている方、
今年こそ「話せる中国語」を本気で身につけたい方は
ぜひ一度ご参加ください。
・中国語ってどんな言語?読めばわかる中国語のすべて
・中国ゼミでは日本人が効率よく中国語をマスターするためのノウハウをすべてご紹介しています。ぜひ実践してください。
・中国語は発音が重要!この記事では初心者にもわかりやすく解説しています。
・勉強のコツのヒントが得られるかもしれません。フルーエントにて中国語を学習されている受講生の声はこちら