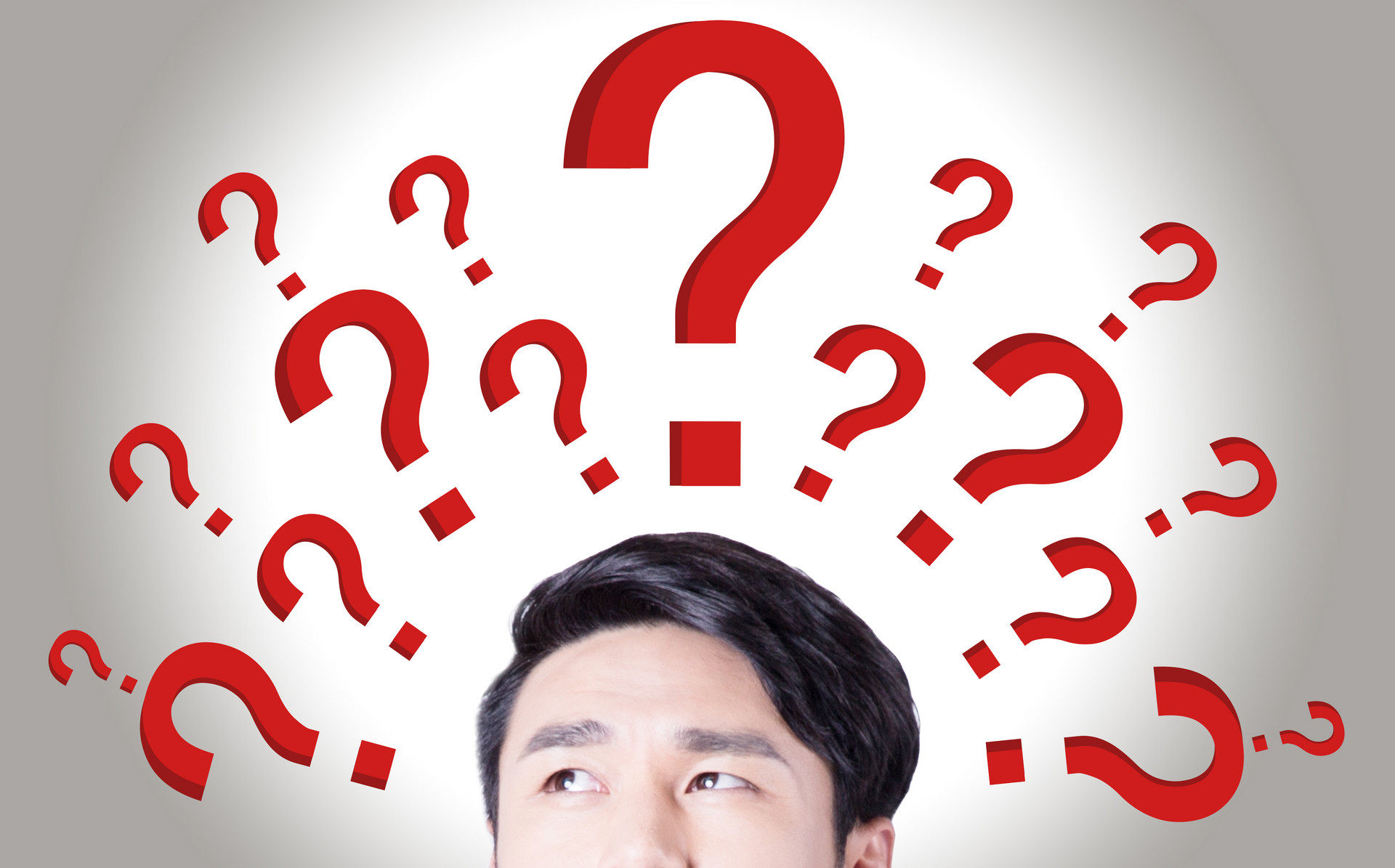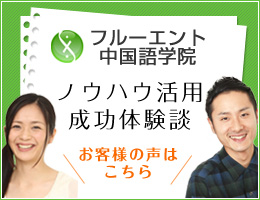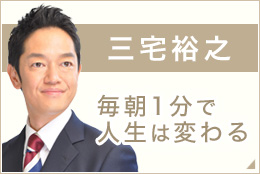中国語で「いただきます」は何と言うのでしょう?
実は中国では、食事前に「いただきます」を言う習慣が無く、「いただきます」にピッタリあてはまる言葉がありません。
でも、日本人なら習慣的に、何か言葉を言いたい!と思う人もいるでしょう。そんな時に使える「いただきます」に代わる表現をご紹介します。また食事の席の会話表現をまとめました。
ぜひ表現の幅を広げ、食事の席での会話を楽しんでください。
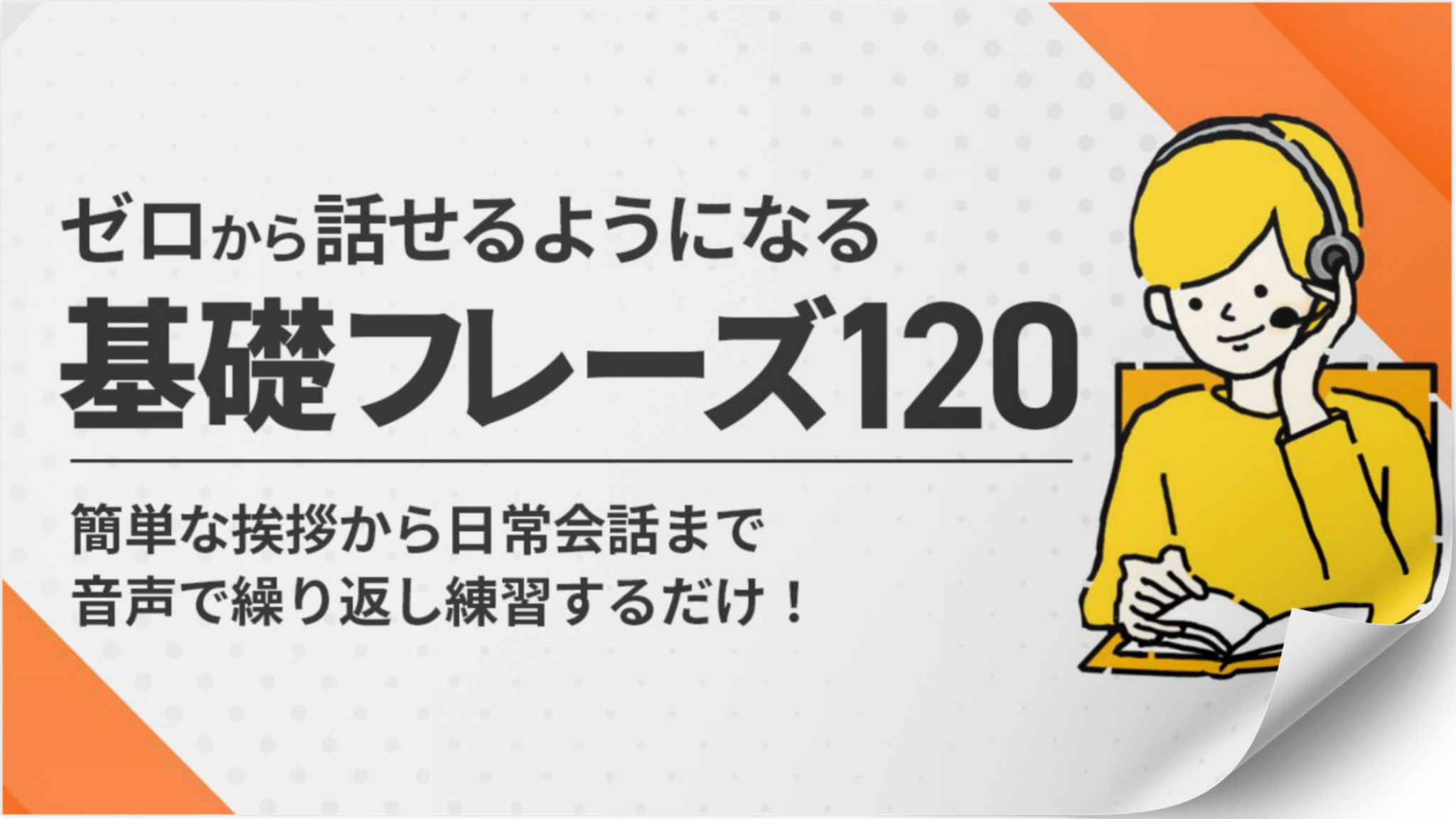
会話フレーズ120選をプレゼント
あいさつ・買い物・食事など、日常のリアルな中国語を厳選。
音声付きだから、フレーズの発音もすぐ真似できます。
スキマ時間の学習にもぴったりです。
\フルーエントLINEに登録して/
今すぐフレーズ集を受け取る目次
1. 中国語にいただきますの概念はない
実は、中国語には「いただきます」の概念がありません。食事の前に言う言葉は特に決まっておらず、何も言わずに食べ始めるのが一般的です。戸惑う方も多いですが、これは中国と日本の文化の違いです。
では、あえて「いただきます」を言いたい場合はどのような表現になるのでしょうか。
こちらの動画では、中国語に「いただきます」はないということ、中国の食事に関するマナーをご説明しています。併せてご覧ください。
1-1. あえて言うなら「我要开动了」「我要开饭了」
あえて「いただきます」を訳した場合「我要开动了(Wǒ yào kāidòngle)」となります。
| Wǒ yào kāidòng le 我要开动了 ウォ イャォ カイ ドン ラ |
これは直訳すると「はじめます」という意味。「これから食事をはじめます」という意味で、こちらもあります。
| Wǒ yào kāifàn le 我要开饭了 ウォ イャォ カイ ファン ラ |
日本映画やドラマの中の「いただきます」というセリフは、中国語で「我要开动了」や「我要开饭了」と翻訳されています。もし中国で、あえて「いただきます」といいたいのであればこのように挨拶するとよいでしょう。ただし、中国には食前の挨拶の習慣がないため、言わなくても失礼にはあたりません。
『中国語の発音基礎|効果的なトレーニング方法|動画・音声付』
効率4倍アップの勉強法セミナーに
参加していただけませんか?
今の勉強法を続ける前に、
一度だけ「正解」を確認しませんか?
✔ 話す・聞く・読む・書くが同時に伸びる
✔ 効率4倍アップの学習設計
✔ 90分・無料
2. いただきますに代わる表現方法
いただきますに代わる表現方法をチェックしていきましょう。直接「いただきます」といわなくても、しっかりと食事の感謝を伝えることができます。
2-1. 「では、食べましょう!」
いただきます、という言葉に近いのが「那我们开始吃吧!(Nà wǒ men kāi shǐ chī ba)」です。これは「じゃあ、食べましょうか!」という意味です。
| Nà wǒ men kāi shǐ chī ba 那我们开始吃吧! ナー ウォメン カイシー チー バー |
2-2. 「ご飯が出来たので食べましょう!」
食事を作った人が「ご飯の用意が出来たので食べましょう!」という呼びかけで使えるのが「吃饭了!(Chīfàn le!)」。
| Chī fàn le 吃饭了! チー ファン ラ |
中国の方を招いて食事を振る舞う場合は、この言葉を使ってください。
2-3. 「ご飯の準備が出来ましたよ!」
これも食事を作った側が「ご飯の準備が出来ましたよ!」という意味で使う言葉です。
| Fàn hǎo le! 饭好了! ファン ハオ ラ |
どの言葉も、目上の人、目下の人関係なく使えます。また、どの言葉も中国大陸でも台湾でも使われます。ただ、台湾では繁体字が使われていますので、漢字が少し異なっていますので注意が必要です。(簡体字と繁体字の違いはこちら『中国語の繁体字と簡体字の違いは?学ぶべきはどっち?』で詳しく解説しています。)
最初にお伝えしたとおり、中国語では「いただきます」を言う習慣がないため、どの言葉も食前に必要なフレーズというわけではなく、言わなくてもまったく失礼にあたりません。
『中国人と楽しく付き合うキーポイント!』
3. 食事時に使える表現
「おいしそう!」「おいしい!」など食事の席で使えるフレーズをまとめました。
3-1. 「おいしい!」
食べ物が美味しかったときは「好吃(ハオチー)」、飲み物が美味しかったときは「好喝(ハオフー)」と言います。
| hǎo chī 好吃 ハオチー |
| hǎo hē 好喝 ハオフー |
なお、この場合「おいしい/おいしかった」という現在形と過去形の区別はなく、いつでも使えます。
『中国語のおいしい「好吃 ハオチー」発音と食のフレーズ34』
3-2. 「(いい匂いがして)美味しそう!」
| Hǎo xiāng ā 好香啊! ハオ シィァン アー |
| Wén qi lái hěn hǎo chī 闻起来很好吃 ウェン チー ライ ヘン ハオ チー |
直訳すると「においをかいだところ美味しそう」となります。中国語の「闻」は、「聞く」と「(においを)かぐ」の意味があり、ここでは「かぐ」の意味で使われています。温かい料理・冷たい料理の区別はありません。
3-3. 「(食欲をそそって)美味しそう」
| Hǎo yòurén ā! 好诱人啊! ハオ ヨウ レン アー |
「人を惹きつける魅力がある」という意味です。
| Kàn qi lái hěn hǎo chī 看起来很好吃 カン チー ライ ヘン ハオ チー |
直訳すると「見たところ美味しそう」。見た目が食欲をそそって美味しそうな料理に使えます。このフレーズも温かい料理・冷たい料理の区別なく使えます。
3-4. 「おかわりください」
「(もうひとつ)おかわりください」は「再来一个(Zài lái yī ge)」。
| Zài lái yī ge 再来一个 ザイ ライ イー グァ |
「个」は「個」の意味なので、どんな料理でも通じますが、料理の形態によって変えると中国語がレベルアップします。同じ料理をもう一人前、注文したいときは「再来一份 (Zài lái yī fèn)」、瓶に入ったビールなどは「再来一瓶(Zài lái yī píng)」が適切です。
| Zài lái yī fèn 再来一份 ザイ ライ イー フェン |
| Zài lái yī píng 再来一瓶 ザイ ライ イー ピン |
中国のレストランでは、お茶は基本的におかわり無料です。お茶が急須(ポット)で供される場合も、湯のみで供される場合も、同じです。このお茶のおかわり、面白い合図があります。ヤムチャで有名な広東省では、急須のフタを少しずらすのが「おかわり希望」のサインなのです。ただしこれは中国全土で通じるサインではないので、注意が必要。サインが通じなければ、店員に「请加点儿茶水(チン ジャ ディェァー チャ シュイ)」と言って追加してもらいましょう。
| Qǐng jiā diǎnr chá shuǐ 请加点儿茶水 チン ジャ ディェァー チャ シュイ |
3-5. 「お料理お上手ですね!」
「您的手艺真不错!(Nín de shǒu yì zhēn búcuó!)」は、日本語で「お料理お上手ですね!」という意味。手料理を振舞ってもらったときに伝えるとよいでしょう。
| Nín de shǒuyì zhēn búcuó 您的手艺真不错! ニン デァ ショウイー ヂェン ブーツゥォ |
その料理がおいしく感じた場合は、素直に表現することで自分の気持ちを十分相手に伝えられるでしょう。「料理上手」と自分の腕前を褒められることは、どんな人にとっても嬉しいものです。
3-6. 「今日の料理本当に美味しかったです!」
ごちそうさまという気持ちを伝えたい場合は「今天的菜真好吃!(Jīn tiān de cài zhēn hǎochī)」という言葉も使えます。
| Jīntiān de cài zhēn hǎo chī 今天的菜真好吃! ジンティェン デァ ツァィ ヂェン ハオ チー |
日本語では「おいしかった」と過去形で言いたいときも、「好吃(hǎo chī)」でOKです。
3-7. 「お腹いっぱいです」
実は、中国にはいただきますと同様に、ごちそうさまの概念もありません。食事を終えたあとの挨拶がないのです。「我已经吃饱了(Wǒ yǐjīng chībǎo le)」は、「お腹いっぱいです」「そろそろ行こうか」の意味を持ちます。
こちらの動画では、中国語にはない「ごちそうさま」の気持ちを伝える方法や、レストランに食事に行った時などに役立つアドバイスをご説明しています。併せてご覧ください。
| Wǒ yǐjīng chībǎo le 我已经吃饱了 ウォ イージン チー バオ ラ |
会食が終わったあとは「どのタイミングでレストランを出るのか…」と悩んでしまう日本人も多いです。食事に満足したあとは「我已经吃饱了(Wǒ yǐjīng chībǎo le)」と伝えることで、食事が終了したことを伝えられますよ。
まとめ
中国には日本のように「いただきます」「ごちそうさま」を伝える習慣がありません。当たり前のように食前・食後の挨拶をしている日本人にとっては、慣れないかもしれませんが、これは中国と日本の文化の違いです。
お互いの文化に触れることで、相手の国をもっと身近に感じられます。中国を訪れた場合や、中国の方と食事をする際は、ぜひ本記事で解説した表現を活用して、食事や会話を楽しんでくださいね。
記事をお読みいただきありがとうございました。
今年こそ
「勉強しているのに話せない」を終わらせませんか?
中国語学習が伸び悩む最大の理由は、
「知識」を増やしても
音と口がつながっていないことです。
三宅式シャドーイングは、
✔ 聞く
✔ 話す
✔ 語順・表現
を同時に鍛える、最も効率の良い練習法。
本セミナーでは、
2,500人以上の指導実績をもとに、
・シャドーイングをやるべきタイミング
・効果が出る人/出ない人の決定的な違い
・HSK・検定対策とどう組み合わせるか
を具体的に解説します。
独学で限界を感じている方、
今年こそ「話せる中国語」を本気で身につけたい方は
ぜひ一度ご参加ください。
・中国ゼミでは日本人が効率よく中国語をマスターするためのノウハウをすべてご紹介しています。ぜひ実践してください。
『初心者が中国語を学ぶ勉強法はこれ!10,000人指導のプロが伝授』
・また「中国語」にまつわる疑問を中国ゼミが徹底解説しています。
『中国語のすべて~四声・ピンインとは?方言は?学習法は?~』