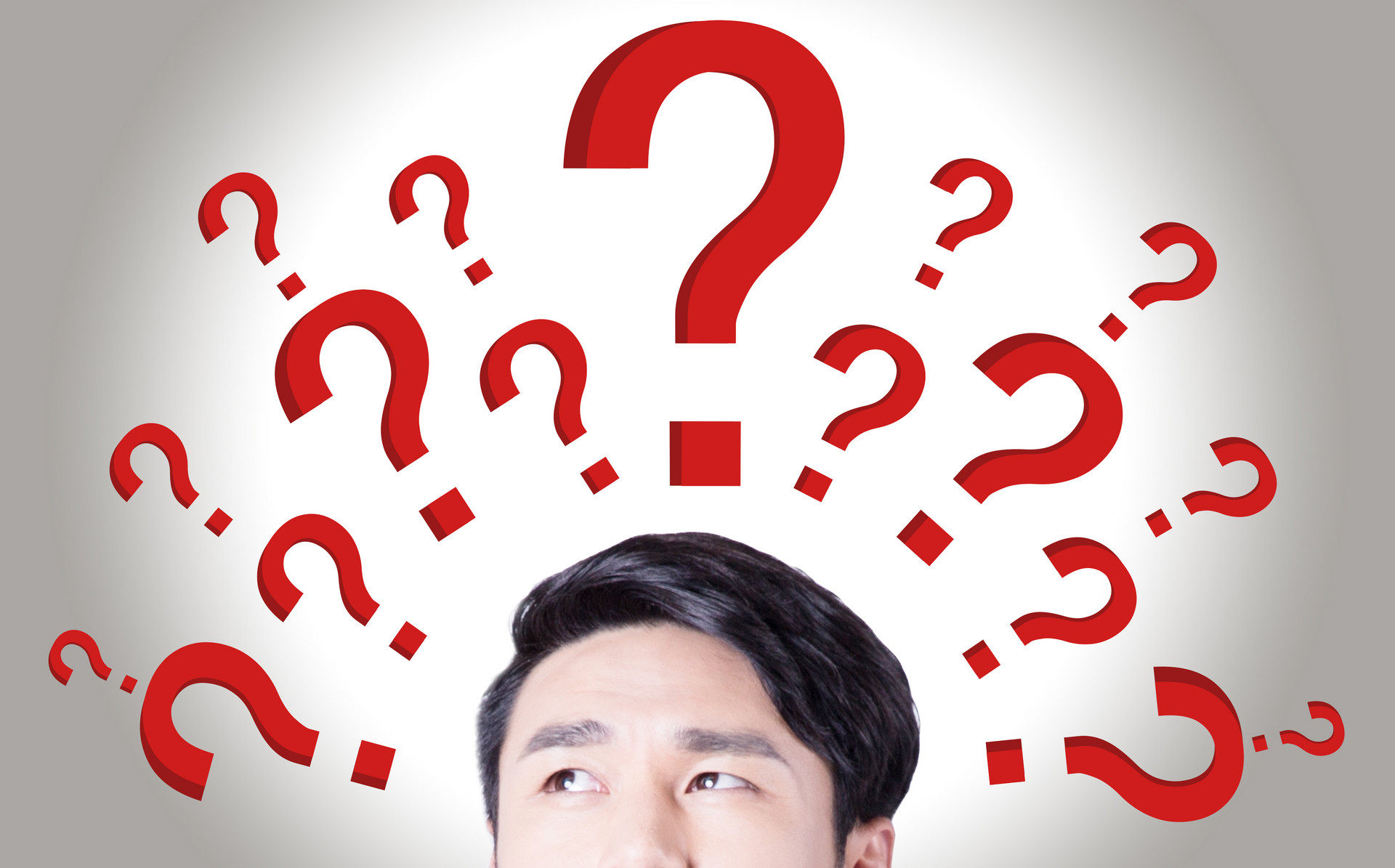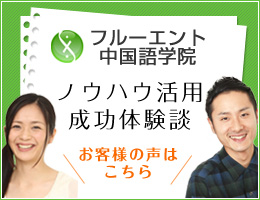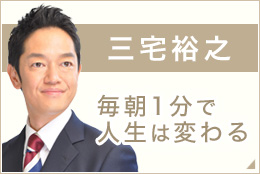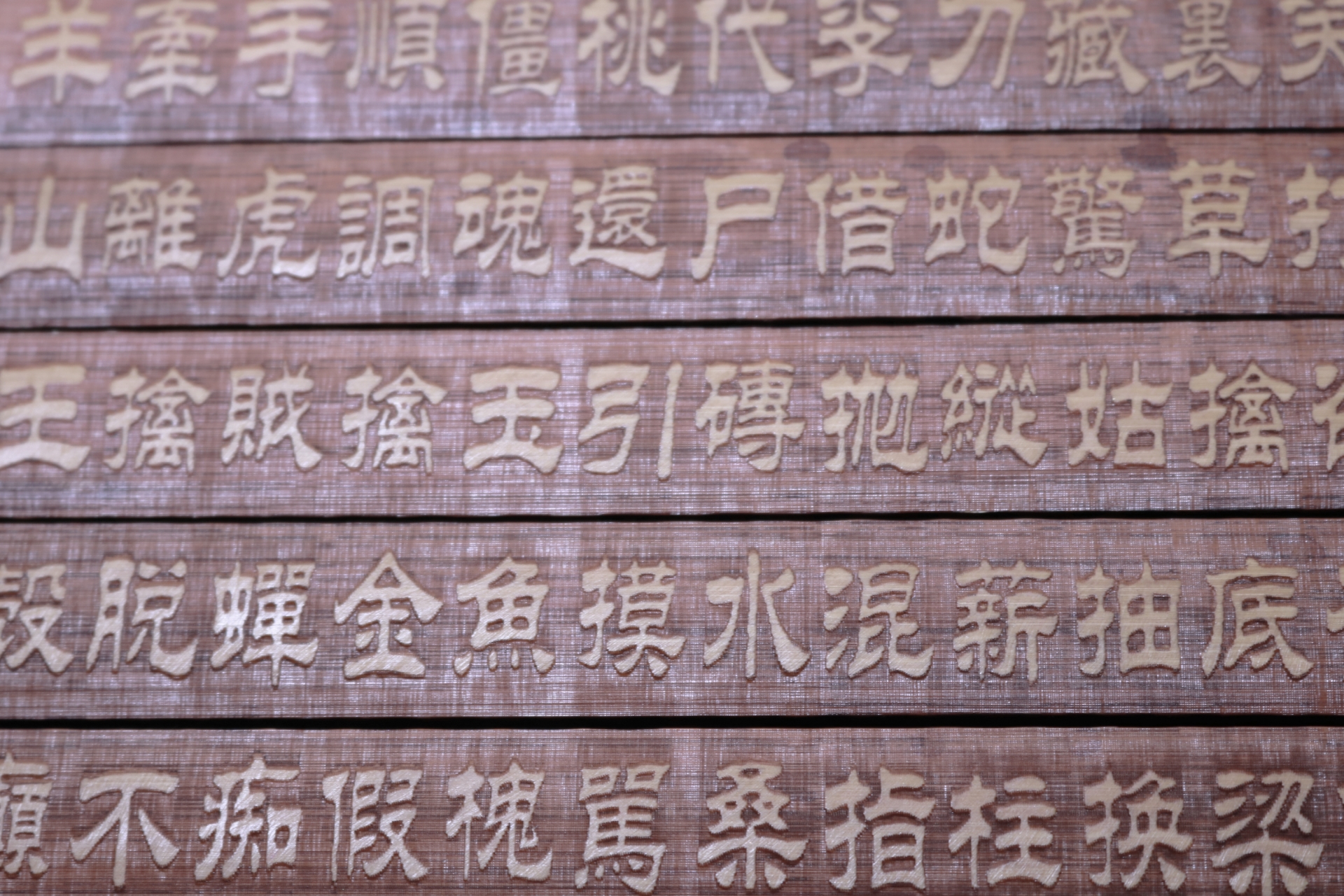
漢詩(かんし)のそもそもの始まりは「詩経」という古代歌謡でした。
紀元前7世紀ごろ成立したと言われるこの歌謡集では、四言を基本に、収穫や一族繁栄の願望、また為政者への不満などがリズミカルに詠まれています。
しかし、これらの歌は特定の作者がありませんでした。その後個人の感情を詠った詩が現れ始め、それぞれの時代の特色を持つ様々なスタイルの詩が詠み継がれてきました。
この記事では先ず漢詩について基本的な説明し、ハートに響く10首をセレクトしてご紹介します。
そして、今まで中国語に触れたことがない方でも、音声を聞きながら真似が出来るよう、中国語の音声を付けて載せてみました。
ちょっとした朗読のコツも加えましたので、このページで繰り返し練習すればあなたにも中国語の漢詩が原語で読めるようになります。
中国人のお友達に聞いてもらうのもよし、宴会の一芸として披露するのもよし、どんどんご利用いただいて、漢詩の魅力に共感していただけたら嬉しいです。
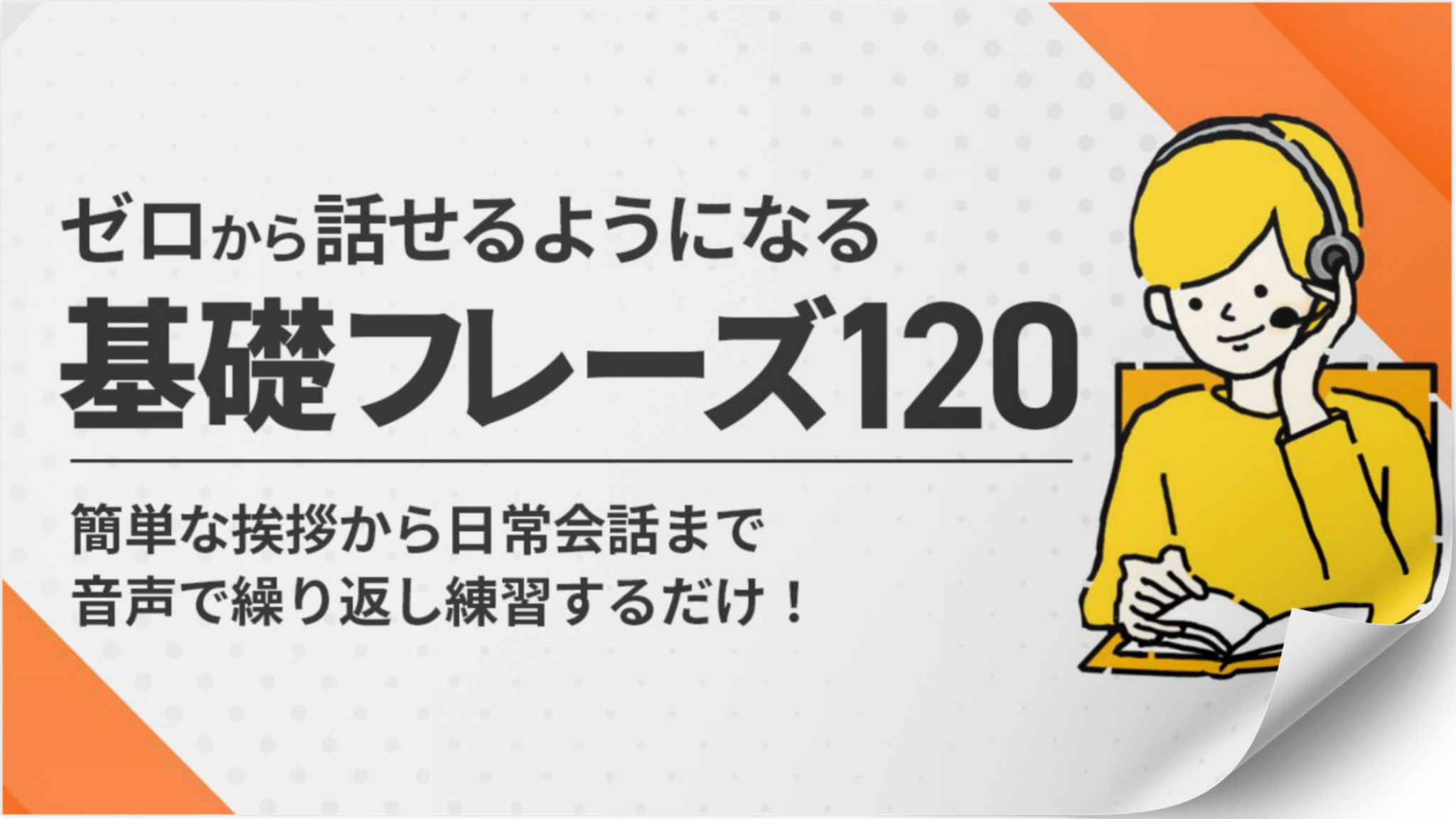
会話フレーズ120選をプレゼント
あいさつ・買い物・食事など、日常のリアルな中国語を厳選。
音声付きだから、フレーズの発音もすぐ真似できます。
スキマ時間の学習にもぴったりです。
\フルーエントLINEに登録して/
今すぐフレーズ集を受け取る目次
0 はじめに〜英雄二人の漢詩を中国語で聞いてみよう
私たちがなぜ古典を愛し、古詩をたしなむか。
それは他でもなく、先人の知恵に学び、現在の自分の人生をより良く生きたいから、ではないでしょうか?
さあ、歴史ロマンと知恵に満ちた漢詩の世界をご一緒に堪能しましょう!
本題に入る前に、中国史を飾る超大物、項羽(こうう)の「垓下(がいか)の歌」と劉邦(りゅうほう)の「大風の歌」をご紹介します。
項羽と劉邦と言えば秦の始皇帝亡き後、天下分け目の壮絶な戦いをしたことで有名です。原語で読む漢詩の響きを感じてみてください。
「垓下の歌」項羽
|
gāi xià gē xiàng yǔ
lì bá shān xī qì gài shì |
| 【書き下し文】 力は山を抜き気は世を蓋う 時に利あらず騅ゆかず 騅のゆかざるをいかにすべき 虞や虞や汝をいかにせん |
| 【現代語 意味】 私の力は山を引き抜くほど、気力は世界を蓋い尽くすほどであった。 私の力は山を引き抜くほど、気力は世界を蓋い尽くすほどであった。 それなのに今は…、時に見放され愛馬の騅も走らなくなってしまった。 騅が走らないのを、どうすればいいのだ、もはやどうしようもない。 虞や虞や、お前の身をどうしよう… |
| 【この詩の背景】 項羽は5年間に渡る戦いの末、垓下の地で劉邦の漢軍に取り囲まれてしまいます。敵兵が歌う祖国「楚」の歌を聞いた部下の兵士たちは、策略にはまり、戦意を失います。これにはさすがの項羽も自信を喪失します。ここから「四面楚歌」という成語は生まれました。 「虞(ぐ)」とは項羽が生涯で愛した唯一の女性で、戦場にも同行していました。項羽がその愛姫と最期の酒を汲み交わしたあと、虞美人は自害したと言われています。 「騅(すい)」とは項羽と共に戦地を駆け抜けた天下の名馬です。 この辞世の詩に「天が我を滅ぼそうとしているのだ」という深い嘆きを込めて、翌日、項羽は壮絶な最期を迎えました。 悲劇のドラマは今なお多くの人の胸を打ち、京劇でも大変な名場面です。『覇王別姫』という映画にもなりました。歴史家・司馬遷も『史記』には皇帝になれなかった項羽を皇帝の伝記である「本紀」に載せています。 |
「大風の歌」劉邦
|
dà fēng gē liú bāng
dà fēng qǐ xī yún feī yáng |
| 【書き下し文】 大風起って 雲飛揚す 威は海内に加はって故郷に歸る 安くにか猛士を得て四方を守らしめん |
| 【現代語 意味】 激しい風が起こって、雲が舞い上がった。 (そのように戦乱が起こったが、ようやく今、平定することができた) 今やわが威光は天下に知れわたり、こうして故郷に帰るのだ。 さあどこで武勇に優れた勇者を集めて これから国を守っていこうか。 |
| 【この詩の背景】 一方、この戦いで“貴族出身、空前絶後の軍事家”である項羽に勝利を収め、故郷に錦を飾った劉邦の喜びに満ちた歌です。名もない一百姓の出身の男でありながら、天下を統一し、中国の代名詞となった強大な大国「漢」の祖となった劉邦。 彼が大成したのは、自分を「部下なしには何もできない」と判断し、いつも優秀な人材を集め、出し惜しみなく褒美を与え、高い地位に就けたから、と言われています。「垓下の戦い」以外は項羽に負け続け、いつも命からがら部下に救われてきた劉邦。一対一では絶対敵わない相手に、勝てた喜びが伝わってきますね。 |
原語で聞く漢詩の趣は如何でしたでしょうか?
では、これからさらに深い漢詩の世界に入っていきましょう。
1 漢詩って何?(近体詩と古体詩)
1-1 古体詩と近体詩
漢詩とは日本で、「漢文で書かれた詩」のことをまとめて呼んでいます。漢詩は大きく分けて、古体詩(こたいし)と近体詩(きんたいし)に分類されます。
| 古体詩(こたいし)…唐代以前に作られた詩 ・1首の句数の形式は不定。古詩(四言・五言・七言)と楽府の二種類。 ・近体詩に比べて明確なスタイルがなく、句法や平仄、押韻の制約も自由。 |
| 近体詩(きんたいし)…唐代以降の詩。漢魏六朝の詩体の通称でもある。 ・1首の句数が、4句のものを絶句、8句のものを律詩、12句以上からなるものを排律(長律)と呼ぶ。 ・1句の字数では、5字からなる五言と、7字からなる七言がある。 ・唐以後に定められた厳格なルール(句法や平仄、韻律など)ある。 |
1-2 近体詩の規則
近体詩は、字数・句数の形式と、平仄(ひょうそく)や押韻のリズムのルールが厳格に決まっています。
近体詩の字数・句数の形式
| 近体詩の種類は一般的に以下の4つ ・五言絶句…一つの句が五文字、ぜんぶで四句 ・七言絶句…一つの句が七文字、ぜんぶで四句 ・五言律詩…一つの句が五文字、ぜんぶで八句 ・七言律詩…一つの句が七文字、ぜんぶで八句 |
平仄(ひょうそく)とは
平仄(ひょうそく)とは、中国語における漢字音を、中古音の調類(声調による類別)にしたがって大きく二種類に分けたもの。発音上のルールで、漢詩においてとても重視されます。
すべての漢字(国字を除く)は、「平声」又は「仄声」の何れか(場合によっては両方)に属しています。
平仄(ひょうそく)の分類と音の特徴
| 「平」…平声(ひょうしょう)。漢詩では重視されます。 ・平声は、平らな音で、陰平(第一声)と上がる音陽平(第二声)に分かれる |
| 「仄」…上声(じょうしょう)・去声(きょしょう)・入声(にっしょう)をまとめて仄声(そくせい)と呼ぶ ・上声…一旦低く下がって上がる音、第三声に当たる ・去声…下に下がる音、第四声にあたる ・入声…短く詰まる強い音。現代標準語では消失している |
中国語には声調があります。声調とは音の上がり下がりの調子のことで、例えば「マ」という音ひとつにしても、上がり下がりの調子が違えば意味も違ってしまいます。漢詩では、この声調を、一定のルールに従って織り交ぜ、リズミカルな詩を作るのです。(※声調については『【音声・動画付】これで解決!四声(声調)の発音と入力』で詳しく解説しています。)
平仄(ひょうそく)の規則の一例「二六対,二四不同」
| 「二六対」…1句の中の2字目と6字目の平仄を同じにしなければならない 「二四不同」…2字目と4字目の平仄が異ならねばならない |
押韻(おういん)とは
漢字一字一字は、全て一音節の発音を持っています。詩のリズム感を出すために、決まったルールにしたがって、同じ音を持っている単語をくり返し使うことを「押韻(おういん)」「韻を踏む」といいます。
| <押韻の規則> ・原則的に偶数句の末尾で行なう。 ・七言詩ではさらに第一句の末尾でも踏む。 ・五言詩では第一句に韻を踏んでも構わない。 ・七言詩の場合は第一句で韻を踏まないのは稀。古体詩は途中で韻の種類を換えても構わないが、近体詩は最後まで同じ韻を用いなくてはならない。 |
絶句の起承転結
絶句(五言絶句、七言絶句)についていえば、起承転結がはっきりしていて、各々を「起句」「承句」「転句」「結句」とよんで区別します。
四コマ漫画のように、起承転結の構成や展開がはっきりしているのが、絶句の大きな特色です。
例えば、「春眠暁を覚えず」で有名な「春暁」では以下のようになります。
| 春眠不觉晓 ←起句 处处闻啼鸟 ←承句 夜来风雨声 ←転句 花落知多少 ←結句 ※赤字は韻を踏んでいる箇所。 |
難しい言葉が沢山出てきましたが、漢詩について少しでも親しみをもっていただけたでしょうか?
2 こんなに魅力的な漢詩の世界
漢詩の魅力といえば、短い詩のなかに一枚の絵が描かれていることでしょう。
例えば、五言絶句ならたった20字の中に、風景と作者の心情や人生訓などが盛り込まれ、それがリズミカルな歌となっていて、さながら音楽付きの絵、という感じでしょうか。
また、「春眠暁を覚えず」「少年老い易く学成り難し」「人間至る処青山有り」など、詩の一行が諺や慣用句となって日本でも親しまれているものもあります。
あるいは、歴史好きの方には、歴史上の人物を詠んだ詩がロマンをかきたてられるのではないかと思います。
3 グッとくる漢詩ベスト10
さぁ、これからいよいよ実際の漢詩を紹介していきます。
中国古代史や漢詩を学び始めると、そこから日本語になった言葉が多いことに驚きます。明治以前に生まれた日本人にとって、漢文は身近な教養だったのですね。
自分の人生経験を積み重ねるにつれ、古人が同じように感じた喜怒哀楽に自らの想いを重ね感慨深い思いに浸れるのも人間らしさではないでしょうか。
現代日本では教養として失われつつある漢詩の世界を、まずは日本語の書き下し文と現代語の意味で味わってみましょう。
4章で原文と、朗読の音声をご紹介します。
歴史ロマン好きなあなたに贈る3首
①「越中覧古」李白
春秋戦国時代に、「呉」の王・夫差(ふさ)と「越」の王・勾践(こうせん)の激しい戦いがありました。「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」「呉越同舟(ごえつどうしゅう)」「会稽(かいけい)の恥を雪(すす)ぐ」という言葉が生まれた、その故事を元に歴史ロマンを詠った栄枯盛衰の詩です。
| 【書き下し文】 越王勾踐 呉を破って帰る 義士 郷に還って尽く錦衣 宮女 花の如く春殿に満つ 只今 惟だ鷓鴣(しゃこ)の飛ぶ有り |
| 【現代語 意味】 越の王・勾踐は呉を破り、会稽での恥をすすいで、故郷に戻ってきた。 従っていた将兵たちはそれぞれ故郷に錦を飾った。 春の宮殿には女たちが花のように満ち溢れている。今はただ、荒れ果てた地に鷓鴣が飛んでいるだけである。 |
| 【この詩の背景】 題名の「越中」は越国の国都・会稽。「鷓鴣」はキジ科の鳥のこと。 越王勾踐は呉王夫差に会稽の地で大敗し、屈辱的な和議を結ばされます。勾踐はその屈辱を忘れず、22年の時を経て夫差を打ちました。夫差が破れたのは、勾踐が贈った絶世の美女・西施に心を奪われたからだと言われています。戦国時代の美女は武器でもあったんですね。 |
②「赤壁」杜牧
「三国志」といえば、男性なら一度は読んだことがある物語ではないでしょうか。『レッドクリフ』という映画にもなりましたね。
赤壁の戦い(208年)は、孫権・劉備連合軍が曹操軍を破った有名な戦いです。この時、孫権軍の最高司令官周瑜は、武将黄蓋の策を容れて魏の船団の密集している所を焼き討ちにします。この策が成功するにはどうしても東南の風が吹くことが必要だったのです。それを孔明が天に祈って風を吹かせたという話です。
周瑜公瑾(175年-210年)は「美周郎」などといわれ、大変なイケメンだったようです。『レッドクリフ』ではトニー・レオンが演じていました。詩の中の「二喬」とは、呉の喬玄の美人姉妹・大喬と小喬のこと。姉の大喬は孫策に、妹の小喬は周瑜に嫁ぎました。まさに歴史の陰に女あり!ですね。
血なまぐさい男達の熾烈な戦いの世界に見え隠れする美女の存在。歴史ロマンを一層かきたてますね。
| 【書き下し文】 折戟(せつげき)沙に沈んで 鉄未だ銷せず 自ら磨洗をもつて 前朝を認む 東風 周郎の与に便せずんば 銅雀 春深うして 二喬を鎖(とざ)さん |
| 【現代語 意味】 砂の中に折れた矛が埋もれていた。 掘り出してみると鉄はいまだにさび付いていない。自分で磨いてみると、まさに三国時代のものとわかった。もし赤壁の戦いで、呉の周瑜や蜀の諸葛亮が望んだように東風が吹かなかったら、美人で名高い大喬・小喬姉妹は魏の宮殿「銅雀台」に捕らえられ、曹操の慰みものにされていただろう。 |
※「折戟」…折れた矛。「未銷」…まだ錆びていない。「前朝」…以前の王朝。三国時代。「銅雀」…曹操の宮殿。銅雀台。
③「春望」杜甫
「越中覧古」のようにかつて栄えた場所が見る影もない…という想いを詠んだ詩で有名なものはやはり杜甫のこの詩でしょうか。杜甫(とほ・712年-770年)は盛唐の人で李白とともに唐代最高の詩人として知られています。
これは杜甫がかつては栄華を極めた長安の荒廃した様を見て詠んだ詩です。作者46歳の作。詩の前半は眼の前の光景を見て、変化する人の世と、変わらない自然とを対比させて感慨にふけり、後半は国を憂い、妻子を想い、心労によって急激に衰えた我が身を嘆いています。草の生い茂る春の野原に呆然と立ち尽くす武将の姿が目に浮かぶような作品です。
| 【書き下し文】 国破れて山河(さんが)在り 城春にして草木(そうもく)深し 時に感じては花にも涙を濺(そそ)ぎ 別れを恨んでは鳥にも心を驚かす 烽火三月(ほうかさんげつ)に連(つら)なり 家書(かしょ)萬金(ばんきん)に抵(あた)る 白頭(はくとう)掻(か)かけば更に短く 渾(す)べて簪(しん)に勝(た)えざらんと欲(ほっ)す |
| 【現代語 意味】 国都長安は戦乱のために破壊されてしまったが、自然の山や河は昔どおりに残っている。この城内は春になっても、草木が深く生い茂っているだけだ。人陰すら見えない。自分はこのいたましい時世を感じ、平和な春ならば花を見て楽しいはずなのだが、かえって花を見ては涙をはらはらと流してしまう。家族との別れを恨み悲しんで、心を慰めてくれるはずの鳥にも心を驚かされる。戦火は三ヶ月もの長い間続いている。待ちわびる家族からの手紙は、万金にも相当するほど貴重に思われる。自分の白髪頭をかくと、心労のために髪の毛も短くなってしまい、役人が頭につける冠をとめるかんざしも挿せないほど薄くなってしまった。 |
情緒あふれる詩がすきなあなたに贈る5首
さて、歴史ロマンを味わった後は、情緒の世界に浸ってみましょう。
中国の古人の人生に対する様々な想いに私たち現代人の喜怒哀楽もそっと重ねてみたら…。どんな思い出のシーンやその時の想いが皆さんの胸に湧き上がるか…楽しんでくださいね。
④「桃夭」(詩経)詠み人知らず
中国最古の詩集「詩経」で大変有名な一首です。嫁いでいく娘に親が贈る祝いの言葉に昔も今も変わらない親心を感じますね。桃を詠うことで若い娘を連想させたり、韻を踏んだり、詩の完成度としても格調高いものです。
大切な方の結婚式でこの詩の意味と謂われを説明して、中国語で朗読すると喜ばれるかもしれませんね。
| 【書き下し文】 桃の夭夭(ようよう)たる 灼灼たり 其の華 之の子 于(ここ)に帰(とつ)がば 其の室家に宜しからん 桃の夭夭たる 有フン(ゆうふん)たり 其の実 之の子于に帰がば 其の家室に宜しからん 桃の夭夭たる 其の葉蓁蓁(しんしん)たり 之の子于に帰がば 其の家人に宜しからん |
| 【現代語 意味】 桃の木は若く、その花は燃え立つようだ。 この娘が嫁に行ったら、その嫁ぎ先にふさわしい妻になるだろう。 桃の木は若く、その実はふっくらと豊かだ。 この娘が嫁に行ったら、その嫁ぎ先にふさわしい妻になるだろう。 桃の木は若く、その葉はふさふさ茂っている。 この娘が嫁に行ったら、その家の人みんなに喜ばれるだろう。 |
⑤「鸛鵲楼に登る」王之渙
この詩のように各句が対句で構成されている絶句を「偶体絶句」と呼びます。例えば、白と黄色の色の対比、山と海という景色の対比、一と千という数字の対比などです。
この詩は、夕日に染められた山と悠々と流れる黄河の雄大な風景が絵画のように目の前に広がります。最後の一句「更上一層楼」は、もっと遠くまで眺めようと更に高い階へ登っていく作者の心情を表し、人々のもっと努力して次の成果を掴みたい想いと重なります。
現代でも、もっと○○したいという目標を目指している状況のときに「“更に上る一層の楼”って言うでしょ?頑張らないとね!」というふうに日常会話で使われる有名な詩のひとつです。
| 【書き下し文】 白日(はくじつ) 山に依って尽き 黄河 海に入って流(なが)る 千里の目を窮(きわ)めんと欲すれば 更に上る一層の楼 |
| 【現代語 意味】 白っぽい光を放った太陽が山に沈んでいき 目の前を流れる黄河は海に向かって流れている この雄大な景色を千里先まで見極めたいと 更にひとつ上の階へと登った |
⑥「春暁」孟浩然
「春眠暁を覚えず」と言えば、現代日本人にもおなじみの一句です。作者の孟浩然は唐代の詩人。40歳を過ぎて役人になったものの科挙に合格せず、一生ぶらぶらして過ごした自由詩人だったようです。布団の中でまどろみながら「昨日の雨風で花がどれくらいちってしまったかなぁ…」と心配しているあたり、やはり呑気な人物像が浮かびます。
| 【書き下し文】 春眠暁を覚えず、 処処(しょしょ)、啼鳥(ていちょう)を聞く。 夜来風雨(やらいふうう)の声、 花落(お)つること知んぬ多少ぞ。 |
| 【現代語 意味】 春の夜の眠りは心地よく、朝が来たのにも気づかなかった。 あちらでもこちらでも鳥が啼くのが聞こえる。 昨夜は一晩中、雨まじりの風が吹いていたが、 花はどれくらい散ってしまっただろうか。 |
⑦「静夜思」李白
「静夜思」は楽府のお題の一つであり、同じタイトルで多くの人が詩を書いていますが、李白のこの詩が断然有名です。転句と結句が対になっています。
暗い秋の夜に皓皓と光る月の光が作者のベッドまで差し込んでいます。頭を上げて名月とその後ろにうっすら映し出されている山並みとを眺めていると、つい故郷の親兄弟、友人のことが思い出されて、気が付けば、頭を垂れて想いに浸っていた、現代の私たちでも同じような状況、想いになることもあると思います。親しみやすい詩ですね。
| 【書き下し文】 牀前(しょうぜん)月光を看る 疑(うたが)うらくは是(これ)地上(ちじょう)の霜かと 頭を挙(あ)げて山月(さんげつ)を望み 頭を低(た)れて故郷を思う |
| 【現代語 意味】 寝台の前に月光が差している。まるで地面を霜が覆っているかと見まがうほどだ。頭を上げて山ぎわにかかる月を見ていると、懐かしい故郷のことを思い出し、頭を垂れて想いにふけった。 |
⑧「江南」(漢楽府)
この詩は楽府という詩のジャンルに属します。前漢の時代から「楽府」と呼ばれる役所が置かれ、各地の民謡を集めた、とされていますが、秦の始皇帝の兵馬俑と共に発掘された資料に既に「楽府」の記録があるそうです。
この詩の漢楽府とは漢の時代のオリジナルの詩であることを強調しています。江南とは地方の名前ですが、のちに「江南」自体が歌のお題となり、同じタイトルで様々な歌が作られました。これはその中で最も古い、素朴なものです。
| 【書き下し文】 江南(こうなん)蓮(はす)を採(と)るべし 蓮葉(れんよう)何ぞ田田(でんでん)たる 魚(うお)は蓮葉(れんよう)の間(かん)に戯(たわむ)れる 魚は蓮葉の東に戯れる 魚は蓮葉の南に戯れる 魚は蓮葉の北に戯れる |
| 【現代語 意味】 水の都、江南に広がる沼地に小舟を浮かべ、早乙女が蓮を摘んでいる。 蓮の葉は青々と見事に茂り、魚たちは蓮の葉の間を泳ぎ回っている。 こっちにきたかと思えば、またあっちに顔を出す。 |
“江南の広大な沼地に蓮を摘む若い女性がいる。”日本の茶摘みのように蓮の実を摘むのは若い女性と決まっていました。
“沼地に小舟を浮かべて蓮を摘む早乙女の姿と蓮の葉に戯れる魚たち。”この魚は早乙女に戯れる若い男衆だという解説もあるようで、広大な沼地で繰り広げたれた今でいう婚活の風景だったかも、と想像すると微笑ましいですね。
一行五文字で後半は頭の二文字が同じという頭韻、民謡らしいリフレインが印象的な素朴な詩です。
人生の格言に闘志が奮い立つあなたに贈る2首
最後にやはり、人生を良い方向い導いてくれるエネルギー溢れる2首をご紹介します。
⑨「偶成」朱熹
この詩を知らない人は日本人にはいないのではないか、と思われる程ポピュラーな詩ですね。詩吟愛好家の方々にも綿々と愛唱されています。
作者は宋の哲学者・詩人である朱熹。18歳で進士に合格したという天才ぶり。後に我が国の官学ともなった「朱子学」を完成させたことで大変有名な人物です。
こんな人でも、いやこんなに出来る人だからこそ、時間の貴重さを説くのでしょうか。過ぎ去った時間が本当にあっという間であることは、ある程度の年齢にならないと実感できないものですが、限られた時間を有意義に過ごしたいものですね。
| 【書き下し文】 少年老(お)い易(やす)く 学(がく)成り難(がた)し 一寸の光陰(こういん) 軽(かろ)んず可(べ)からず 未(いま)だ覚(さ)めず池塘(ちとう) 春草(しゅんそう)の夢 階前(かいぜん)の梧葉(ごよう) 已(すで)に秋声(しゅうせい) |
| 【現代語 意味】 少年もあっという間に年をとってしまい、それでいて学問はなかなか完成しにくい。 だから、少しの時間でも軽軽しく過ごしてはならない。 池の堤の若草の上でまどろんだ春の日の夢がまだ覚めないうちに、 階段の前の青桐(あおぎり)の葉には、もう秋風の音が聞かれるように、 月日は瞬く間に過ぎ去ってしまうものなのだ。 |
⑩「将に東遊せんとして壁に題す」釈月性(しゃくげっしょう)
最後に日本人の作った漢詩をご紹介します。「男児志を立てて郷関を出(い)づ」と結句「人間到る処青山あり」と言えば、一度は耳にしたことがあるかもしれません。
幕末の勤皇志士たちの精神的な支えであったこの詩は、読むと思わず背筋が伸び、気合いが入ります。
作者は月性(げっしょう)という幕末の尊皇攘夷派の僧。42歳で病没するまで激動の時代を生きた若き僧の想いは詩に託され、今も多くの人の胸に刺さります。
| 【書き下し文】 将(まさ)に東遊(とうゆう)せんとして壁(かべ)に題(だい)す 男児(だんじ) 志を立てて郷関(きょうかん)を出(い)づ |
| 【現代語 意味】 男児たるもの、いったん志を立てて郷里を離れるからには 学問が大成しない限り二度と戻らない覚悟である。 ちゃんとした墓地に埋葬されようなどという考えはとうに捨てている。 どんな場所で野垂れ死のうと、本望である。 |
4 グッとくる漢詩ベスト10を中国語で読む【朗読とコツ付】
今までご紹介した10首を中国語で読んでみましょう。模範朗読について真似してみてください。日本語の書き下し文では味わえない感覚を、原文で堪能して下さい。
①「越中覧古」李白
| Yuè zhōng lǎn gǔ Lǐ-bái 《越 中 览 古》 李 白 yuè wáng gōu jiàn pò wú guī |
【朗読のコツ】
|
②「赤壁」杜牧
| Chì bì Dù mù 《赤 壁》 杜 牧 zhé jǐ chén shā tiě wèi xiāo |
【朗読のコツ】
|
③「春望」杜甫
| Chūn Wàng Dù Fǔ 《春 望》 杜 甫 guó pò shān hé zài , |
【朗読のコツ】
|
④「桃夭」(詩経)詠み人知らず
| Táo yāo Shī jīng 《桃 夭》 诗 经 táo zhī yāo yāo zhuó zhuó qí huá |
【朗読のコツ】
|
⑤「鸛鵲楼に登る」王之渙
| Dēng guàn què lóu Wáng zhī huàn 《登 鹳 雀 楼》 王 之 涣 bái rì yī shān jìn |
【朗読のコツ】
|
⑥「春暁」孟浩然
| Chūn xiǎo Mèng hào rán 《春 晓》 孟 浩 然 chūn mián bù jué xiǎo, |
【朗読のコツ】
|
⑦「静夜思」李白
| Jìngyè sī Lǐ-bái 《静夜思》 李 白 chuáng qián míng yuè guāng |
【朗読のコツ】
|
⑧「江南」(漢楽府)
| Jiāng nán Hàn yuè fǔ 《江 南》 汉 乐 府 Jiāng nán kě cǎi lián |
【朗読のコツ】
|
⑨「偶成」朱熹
| ǒu chéng Zhū xī 《偶 成 》 朱 熹 shào nián yì lǎo xué nán chéng |
【朗読のコツ】
|
⑩「将に東遊せんとして壁に題す」釈月性
| Jiāng dōng yóu tí bì Shì yuè xìng 《将 东 游 题 壁》 释 月 性 nán ér lì zhì chū xiāng guān |
【朗読のコツ】
|
大切なのは朗読技術もさることながら、その詩にいかに自分の想いを込めて詠めるか、ということです。
言葉はエネルギーです。意味を越えて伝わるものが必ずあります!
おわりに
ベスト10ということでご紹介してまいりましたが、漢詩の世界は足を踏み入れてみるとまるで大海の如く、広く深く、グッと想いのこみ上げる詩は本当にたくさんあり、10首に収めるのが大変悩ましい思いでした。
私たち人間が最終的に持ちうるものは感情や想いしかないのだということを、古人の詩を通して感じます。
栄枯盛衰、人は死後の別世界には、この世で得た物質は何一つ持っていけません。多くの人との温かな想い出をもって旅立てることこそ、豊かな人生と言えるのではないでしょうか。
記事をお読みいただきありがとうございました。
今年こそ
「勉強しているのに話せない」を終わらせませんか?
中国語学習が伸び悩む最大の理由は、
「知識」を増やしても
音と口がつながっていないことです。
三宅式シャドーイングは、
✔ 聞く
✔ 話す
✔ 語順・表現
を同時に鍛える、最も効率の良い練習法。
本セミナーでは、
2,500人以上の指導実績をもとに、
・シャドーイングをやるべきタイミング
・効果が出る人/出ない人の決定的な違い
・HSK・検定対策とどう組み合わせるか
を具体的に解説します。
独学で限界を感じている方、
今年こそ「話せる中国語」を本気で身につけたい方は
ぜひ一度ご参加ください。
・中国語ってどんな言語?読めばわかる中国語のすべて
・中国ゼミでは日本人が効率よく中国語をマスターするためのノウハウをすべてご紹介しています。ぜひ実践してください。
・中国語は発音が重要!この記事では初心者にもわかりやすく解説しています。
・勉強のコツのヒントが得られるかもしれません。フルーエントにて中国語を学習されている受講生の声はこちら